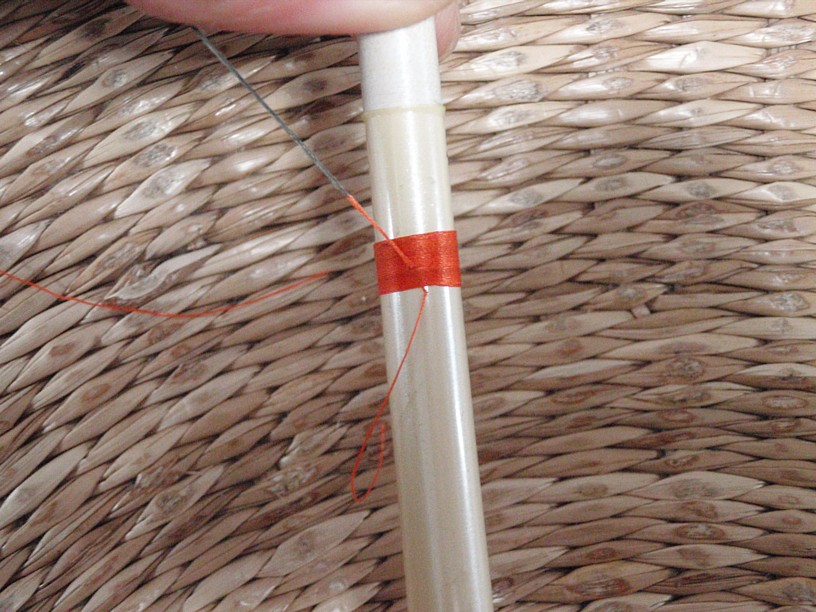|
| ラスコー洞窟壁画、撮影EUX氏、ウィキメディアより |
特に後者は、著作権との関連もあって、法的、倫理的な問題が取りざたされ議論になっている。とある文学賞の新人賞作家が、生成AIの出力文章も使ったと公言して話題になったりもしてた。読む方の、読むのに限らず、観る、聴くその他鑑賞する側の立場としては、純粋に考えると生成AIだろうと巨匠の渾身だろうと、出力された作品が面白いか、面白くないかだけが問題である。開高先生が昔、自分の作品を評して「これが実体験ではなく取材だけで書かれているなら素晴らしい」というようなことをのたまう評論家に対して、そんなもん読む側からしたら関係ない、作品として面白いかどうかだけだ、と言い切ってたのを思い出す。
ただ、生成AIの出力物は作品として純粋に面白いかどうかだけではすまされない、今までの長い歴史で整理されてきた著作権や模倣の概念に当てはまらない事象でもあり、人の仕事を機械が奪うことへの危機感、芸術とはなんぞやに迫るような根本的な問題をも提起されているように思う。特にそのへん顕著なのがイラスト界隈で、そんなもんお客さんが要望したイラストを即座にホイホイと出力できるソフトなんて使われたら、底辺イラストレーターの仕事なんて速攻で無くなりおまんまの食いあげである。ちょっと前までラーメンを箸で食えなかった生成AIイラストとかは、ある種笑いの対象でしかなかったけど、すぐにそんな不具合は修正されて、ネット記事の見出し画像とか生成AIに作らせてるのをわざと分かるように強調したようなイラストも増えたので、気づかないであろうモノも含め確実に普通に使われるようになりつつある。
10年かそこら前に、今後AIに仕事を奪われる職業としてあがってたのは、自動運転に取って代わられる運転手はじめ単純労働者で、逆に芸術や頭脳労働の方面ではAIでは代替しえないとか言われてたのに、真逆のことが起きている。いまだ車は自動運転は実験段階で、多くの単純労働では高度な金の掛かるAIを使ったシステムに置き換わるどころか、安い労働力でありつづける人間がこき使われ続けている。元々コンピューターとかAI(人工知能)とかは人間の脳の機能の模倣というか外部化、機械化であり、人の脳が行っていたようなことを置換していくのは当然の成り行きだろう。脳生理学者がさも自分の研究対象は特別であると言いたげに「脳のシステムは複雑でAIや機械で再現・置換されることはありえない」とか間抜けなことをぬかしているけど、出始めで画素数が少なく荒い画像しか出力できなかった時代のデジカメ写真を見て「フィルム写真に追いつくことはない」とか言ってたマヌケと同じだと感じる。結局写真の場合、フィルムに焼き付ける物質的な分子数なり色素数的なものを画素数が超えれば良いだけで物理的な数の問題でしかなかったのは明白で、アホかと思っていた。同じことが脳でも言える。いくら複雑と言っても、物理的に電気やら伝達物質やら使って神経のつながり(の他にも色々あると分かってきたようだけど)で制御されているシステムであり、簡単ではないにしても模倣や再現、代替は可能なはずで、脳機能全体の代替とかは難しくとも、当座必要な機能の再現ぐらいは存外早く実現するのではと、近年のそのあたりの技術やらの進歩の早さを見ていると思うところである。で、外部化、機械化された脳機能は頭蓋骨という監獄から解き放たれ、大きさの制限がなくなり、最終的にはホモサピの脳を超え、さらなる高度化、複雑化さえなしえるようにも思う。
で、そうやって生成AIに仕事を奪われていくイラストレーターは当然危機感を覚えるわな。で”反AI”的な宗派の人もでてくるのはまあそうなんだろうなと思う。いわく「生成AIがやってることは模倣でしかなく、イラストレーターが居なくなるとオリジナリティーのある絵が生まれなくなる」、曰く「既存の作品を学習のために取り込み、その作品の模倣的な出力を生むのは著作権の侵害である」というのが、主な主張だろうか。確かに頷ける面もある。
ただ、生成AIがやってるのは創造ではなく模倣であるってのは、自分らにブーメラン帰ってきて突き刺さらんのかよ?って思う。すべての作品って言って良いぐらいに創作物って、それまで制作者が観てきたモノ聴いてきたモノ、ありとあらゆる表現ブツの影響を受けまくってるわけで、全くの独自性を持った表現なんてあり得なくて、模倣の先になんかその人独自の個性が生まれてくるぐらいのもんだと思うので、生成AIがやってることとナニが違うと思う。現時点で人間の方が創造的だとしても、これまた時間の問題で人間のイラストレーターがやってる創造的な仕事ぐらいAIがやり始めるのは明白。すべての表現物が何らかの模倣であるってのは極論に聞こえるかもだけど、じゃあイラストレーターは紙もペンもない時代に洞窟の壁に絵を描いたご先祖のような”絵の創造”からみんなやってるのかって言ったらそうじゃないでしょ?紙に描いてるか液晶タブレットで描いてるか知らんけど、そのやり方は少なくとも模倣してるでしょって話。なにしろマンガの神様の一人である藤子・F・不二雄先生が「「まんがをかく」という作業は、情報やアイデアをいろいろと取り入れ、そしてはき出すということのくりかえしといってよいでしょう。つまり、この世の中に、純粋の創作というものはありえないのです。けっきょく、まんがをかくということは、一言でいえば「再生産」ということになります。かつてあった文化遺産の再生産を、まんがという形でおこなっているのが「まんが家」なのです。」(「藤子・F・不二雄のまんが技法」より引用)って言ってるぐらいだから、独自性なんてあるような無いようなあえかなもので、それがあったら超一流って話で、少なくともそういう独自性があるイラストレーターは、もし生成AIが本当に創造性が無く新しいモノが生みだせないなら、学習元としても必要とされるしもちろんその独創性から評価されて生き残るだろうっていう矛盾。そのへん凡百のイラストレーター氏はどう思ってるんだろう。機械やらシステムやらの発達で仕事が無くなるのって電話交換手やらタイピスト(タイプライター打つ人)の例を出すまでもなく、歴史上ありふれた事例であり、新たな便利な技術が使われないで自分たちが保護されるなんてことは無いと覚悟した方がよろしいかと老婆心ながら厳しいことを書いておきたい。「アナタに描いてもらわないとダメなんだ」と顧客に言わせるだけの実力がなく、なんかそれっぽいイラストでも載せとくか、って需要で飯食ってたイラストレーターさんは生成AIのほうが安ければ使ってもらえなくなるよって話。外野の”反AI宗派”の人なんて今はそう言っててもすぐに転ぶから見ててごらん。
もう一つの著作権やら模倣の倫理的問題とかはややこしい。キャラクターやら構図そのモノをパクったのなら著作権侵害を認定するのも比較的簡単だけど、そもそも”画風”を学習させてパクるってなってくると、そんなもんさっきも書いたけどどんな表現者でも影響を受けた先達はいるわけで、じゃあそれは著作権を侵害してるのかっていうとそうでもないってのが普通だろう。例えばワシ全然楽しく読めなくて序盤で挫折した「ワンピース」の尾田栄一郎先生の描く女性の胸から腰のくびれの曲線が、師匠である「ジャングルの王者ターちゃん」の徳弘正也先生のそれを引き継いでるなと思ったりするわけだけど、それを著作権侵害というかと言えば、師弟関係だからってのは抜きにしても言わんよねって話。画風自体はだいぶ違うしね。文句言ってる反AI派のイラストレーターさんだって、いろんな表現物見て模倣もしただろうし、影響も受けただろう、そうやって自分の絵柄を育てたんでしょ?同じことAIがやってるだけじゃん、ってなる。でも、そうはいっても話題になってた「ジブリ風イラスト」とかはさすがに宮崎駿先生あたりには、著作権侵害と認めさせるのは難しくとも怒る権利があるだろうと思う。そのへんの線引きは生成AI云々以前に、人間同士でさえも微妙で「ある作品の一部をパクっても、そこに愛があれば「オマージュ」である」とか言われるぐらいで、文学の世界とかでは伝統だけど、パロディーやらオマージュ、本歌取り等はなくてはならんぐらいの表現手法の一つでもある。ワシも今回の題はディック先生の”アンドロ羊”への愛を込めてオマージュさせてもらったつもりである。まさにアンドロ羊はAIが娯楽を求めうるか的な今まさに起こってるような事象を予見する傑作だと思う。ちなみに手塚治虫神の娘さんは「ライオンキングは許せても、田中圭一はゆるせません」と、手塚先生の画風でエログロナンセンスを描きまくった田中先生のマンガの推薦帯に書いておられた。っていうぐらいにあるときは許され、あるときは怒られるのが”パクリ”の実態であり、線引き難しいよって話で、制度的な話については新しく出てきた事象でもあり、学習元を特定できる形で取り込んでるのかとか技術的な難しさもある中でどうするか専門家に考えてもらうしかないけど、表現を楽しむ側の姿勢としては、それが許されるモノかどうか?きちんと考えてイヤなモノは拒否して視聴購読等しない、ってその判断のセンスが求められるのではないだろうか。あからさまのパクリで楽して銭儲けやがる輩の作品など蹴っ飛ばせだけど、健全な笑えるパロディーやら元ネタへの尊敬と愛に満ちたオマージュは制作者と共に楽しむべきだろう。ってのが間違えたくない基本路線だとワシャ思うのじゃ。
っていうのを考えるきっかけになったのが、最近視聴した「未ル わたしのみらい」というアニメの第3話で、このアニメ、なんか人間やら動物やらに変身できるある種の神のように偏在するAI搭載のロボット”ミル”が、人を助けたりしつつ自身も学習し成長していくという基本一話独立のオムニバス形式の物語なんだけど、3話目で才能ある超絶技巧のピアニストの卵がアルバイトでその技術をAIに学習させるかたちで科学者に協力していたら、本人事故で片手の自由を失うんだけど、本人の技術を学習させていたAIに補助させる特殊な義手が科学者によって開発されて、結果演奏家として成功を収める。だけど、果たしてその表現はそのピアニストのモノなのか否か?ってな脚本で思考実験としてとても良くできた例題であり唸らされた。作中でも開発した科学者への取材で「でも機械が弾いてるんでしょ」とか、まあそういう意見もございますわなってことも言われて、でもその技術はもともと彼女のものを学習させたモノで彼女の技術なんです、っていう整理はあっても口さがない連中はネットとかでお気楽に「こんなの芸術じゃない」とか批判を書き込むのを本人目にしてしまったりしたら、そりゃ苦悩するよねって話。明確な答は無いんだろうけど、それでも今回聞き役に回ったミルは、君の表現は君のモノであり、その感動は自分にも引き継がれていく的な救いのある言葉をピアニストにかけている。パクリの問題を排除してAIの補助を受けてなしえた表現等が芸術たり得るか?たり得るでしょ?ってワシャ思うけど、それも程度問題で例えば脳の補助をするAIじゃなくて、体の機能を補助するパワードスーツとかを使って陸上競技とかで記録を出したときに、それが認められるかとかで考えると、陸上競技ならもちろん認められない。ただ、競技の枠があるからダメなだけで、陸上競技でなければ、例えば作業現場で重い荷物運べたら便利で評価できる。あとは費用対効果とかの話になってくる。でもAIに補助させた、あるいは直接作らせた作品を評価する際に、陸上競技のような明確な線引きができるルールがあるかというと、これまで無かったように思う。もちろん盗作はダメとかごく基本的なルールはあるし、読み物なら純文学かラノベかノンフィクションかとかいうゆるい線引きもある。あるけどいつも書くように、線引きなんか関係なくて面白いモノは面白いしつまらんものはつまらんぐらいしか評価する際の基準ってないように思う。そういうなかで、AIを上手く使えば良いモノができるなら使ってもらえば良いじゃん、と楽しむ側として無責任で正直な気持ちもある。あるけど、AIがまるっと作った極めてデキの良い表現物で感動させられてしまう自分っていう図式を考えると、なんか敗北感がただよったりして複雑な乙女心なのである。芸術ってそんなんで良いんだろうか?まあ、すぐに答えがでるような話ではないし、実際に技術が発達していく過程で紆余曲折あってなるようにしかならんのだろうけど、行き着く先がAI様にご提供いただく芸術作品を楽しむだけで、人類が芸術を生み出さないっていう極端なディストピアではなく、なんか良い塩梅の落としどころに落ち着いて欲しいとうすぼんやりと願うのみである。
で、このアニメのもう一つ面白いところが企画・制作が「ヤンマー」だということで、最初そんな名前のアニメ制作会社があるんだと思ってたら、もろに”ヤンボーマーボー天気予報”の農機具製作会社ヤンマーが異分野参入でアニメ作ってるって話で、わりと驚いたし面白がっている。地上波テレビ(変換候補筆頭に”痴情派”と出て笑った)がここまで斜陽化するとヤンボーマーボーでスポンサーになってもろくに宣伝にならんとかあるんだろうか?クソみたいな番組しか作られなくなってるなら自社で作ってしまえというのであればその意気や良しである。で、一話目がもろにアニメ化もしている幸村誠先生の傑作マンガ「プラネテス」のユーリのペンダントのエピソードと同じような話で、分かっててやってるのかどうか疑問符が頭の上に浮かんだけど、3話まで見て確信的にオマージュでやってるなと思うに足りる感じである。なんならプラネテスの元ネタの筋書きをAIにぶち込んで脚本書かせてるんじゃないかぐらいの実験的なことをやっててもおかしくないぐらいに思うほど、いまのところデキが良い。ヤンマーのトラクター買う予定はないけどアニメは引き続き楽しみに視聴させてもらうことにする。
AI様が表現者の仕事を、どの程度になるか分からんけどなんぼかは肩代わりしていくようにはなっていくのかもだけど、今のところまだ人間の作る表現物は面白く楽しめている。まあ、たとえAIに勝てなくなったとしても、表現者は表現することをやめないだろう。と、ゼゼコの一銭も稼げないブログを長らく書き続けているお気楽な表現者としては思うところである。表現することの楽しさをAI様が助けてくれることはあっても肩代わりしてくれることはないだろう。多分きっと、そうあって欲しいと願う。でも、ワシの芸風を学習させた生成AIにこのブログまかせて、マニアックなリールの記事とか書き始めたなら、それはそれで読んでみたいとも思ったり思わなかったりする。